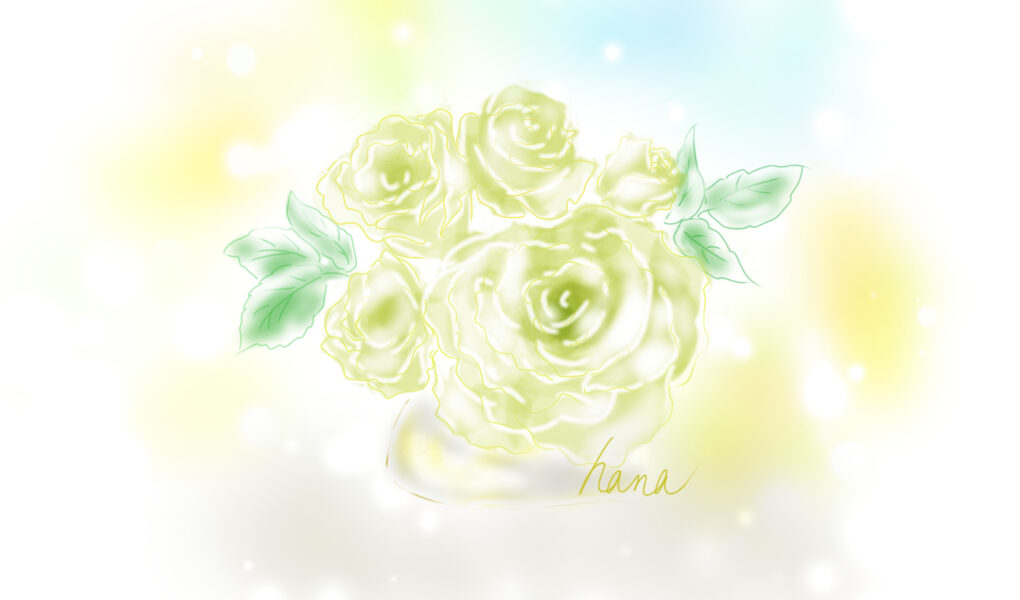1
素肌をくすぐる乾いた風にカエデや赤松の葉が小刻みに揺れまどう。
シジュウカラやホオジロが棲息する森は、どこからともなく湧き出る活力でかすかにさざめいていたが、小波を掬いあげる櫂の音のギーカタ、ギーカタという秘密めいた調子がひびきわたると、急速にせまった宵闇のなかに思わせぶりな風情を横たえていった。
人目の届かぬ闇ほど、誰かさんにとっては恰好の味方というわけで、木々の葉越しにチラチラと見えていた外灯の投光範囲から抜け出ると、ボルドー産のクラレットをグラスにそそぐ娘のためにボートをあやつる若い男は、心密かに微笑んだ。
「おお、俊一。腕は確かなの」フリルのついた白いブラウスの胸元を気づかいながら女が甲高く笑った。
心乱れたからではない。乱れているといえば、もうずっと最前からそうで、いまはむしろピークを過ぎて冷静になってきているとさえ言える。好ましくはないだろう揺れを与えたあとで、男は自己分析しながら女に笑い飛ばした。
「ちょっと感覚がつかめなかっただけですよ。ほら、もう大丈夫でしょう?」
彼は色白で身長は一八〇センチほどあったが、どちらかというと華奢なタイプで、そのうえ遠慮がちな性格のせいか自己主張もへただった。野性味に欠けて、その嗜好の男たちに甘やかに言い寄られる機会がなくはなかった。だがどちらかというと、ご多分に漏れず女が好きだったのである。
彼女は青と白のストライプの柄が際立つ分量の多い生地のスカートを身に着けていたが、それをあまりに無造作にたくしていたため、グレーのストッキングでおおった形の良い脚が、横のほう太股まで露になっていた。それもいまは宵闇のせいではっきりとは見えなくなってきている。
彼女の態度がここまで挑発的だったことがいままであったろうか。首をのけ反らせて飲料を干し、そのまま空を見つづけているかと思うと、辺りの音に耳を澄ませてじっと動かずにいる。そんな瑠衣子のようすに、俊一は無遠慮な視線を投げながら考えた。目のやり場に困ることはない。彼女が彼をまともに見ることなどほとんどないからだ。いままでもそうだった。
だから、男はいくらでも好きなだけ、彼女のことを眺めまわすことができるのだ。昔からそうだ。
彼は彼女のいとこだという理由で顔を合わす機会もしばしばだったが、「瑠衣子お姉ちゃんに手を貸しておあげ」と大人たちに言われながら、節句の飾りつけや庭掃除のときなど、その手伝いや真似事でいつでも二つうえの彼女のそばにくっついていられたのだ。
高輪台のマンションから白塀を巡らせた久ガ原の家に、休日ごとに彼女を訪ねるのが好きだった。
母親は商社の重役である亭主の愚痴をこぼしに実家を訪ねたが、俊一は彼女に会う目的で、オールドローズをからめた蔦のアーチの門をいそいそとくぐった。
幼いころ、世話係の女に髪を梳かれる瑠衣子はミルキーな匂いがしたが、十代からこっちは高価なソープや輸入香水の匂いがその気配に混じっていた。