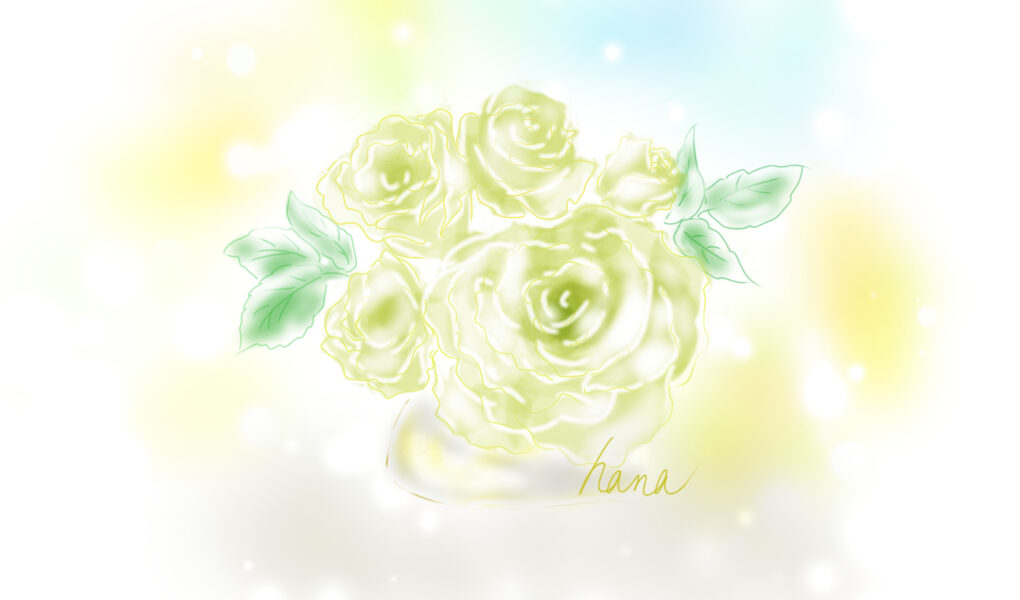1
俊一は潮風に打たれていた瑠衣子の横顔を思い出し、その心に寄り添えないことの寂寥のようなものをそのとき抱いていた。別室に行きテレビをつけたが、音量を上げる気になれなかった。「きみもルイにしてやられているの」という青山雄太の問いかけが頭のなかを巡っていた。
瑠衣子と友人たちとの交流はその後も変わらなかった。彼女はニューヨークに行っていない。少なくとも青山雄太が滞在したであろう期間には――。他の友人たちが行ったかどうかは俊一には分からない。瑠衣子に訊ねてみたいとも思わなかった。
いま俊一は瑠衣子の向かいにいる。櫂をあやつり、瑠衣子を独り占めしていた。
ボートは闇のなかをすべっていたが、月明かりが水面をキラキラと躍らせていたし、もう少しの辺りからは向こう岸の桟橋の支柱が月光に反射する様子も見えるようになるから、夜間の漕ぎ手になったからといって行き先に困るようなことはなかった。
男とふたりで会おうとしない瑠衣子、というのは本当だろうか。
それについて俊一はまったく否定的だった。裕三の会社で創業祭や懇親会などのパーティーがあるときなど、周囲の勧めで瑠衣子も顔を出すことがあった。そんなとき、決まって複数の男たちに取り巻かれて楽しそうに談笑していたからだ。性格が変わったように気さくな笑顔を振りまくのだ。時には初対面の年長の男と消えることさえあった。父親の会社の関係筋ということで瑠衣子なりに気を使っていたのか、そんな解釈もできなくはなかったが、伴う親密な状況を想像して俊一は心穏やかではなかった。裕三は寛容で、どんな瑠衣子のこともにこやかに見守っていた。瑠衣子が刹那的にも男との出会いを楽しんでいたのだと俊一は素直に感じていたが、実際のところ彼女のふるまいの根拠などなに一つ推し測ることができない。複数の男たちとその場から消えたとしても、その後は行動を共にせず建物の前であっさりと左右に別れたのかもしれないし・・・・・・。一対一で向き合うとき物事を動かす主導権はどんな場合も瑠衣子が握っていたから、しばしばつかみ所のない瑠衣子のことを第三者は様々に想像することができた。
いまは、瑠衣子が自分の前にいる。初めてその悦びに与かる者としては都合のいいように解釈したかった。きっと彼女は前からこうしたかったのだ。とっておきの甘えた態度を、群がる男たちにそれぞれ分散する代わりに、年中そばにいながら内気という鎧で装備した目前のいとこに出したくてうずうずしていたのだ。彼の隙や誘いかけが足りなかったのだ。俊一はそのことを反省した。
「引き返しましょうよ、俊一。疲れたわ。さあ、一杯やって。それからUターンよ」
グラスをさしだす手が体ごと揺れ、小宇宙でひるがえる液体がきらめいた。瑠衣子は倒れ込みそうなのを必死でがまんしているといったようすでバランスをとっていた。
午後も、まだ日の高いうちからアルコールをやりはじめて、彼女はすでにワイン以外の十種類ほどのカクテルを何杯ずつか賞味していた。その勢いか、普段はどんなに彼が誘っても舟遊びなどしなかったくせに、きょうはこうしてついてきたのである。そして、ますます闇は垂れ込めようとしていた。心憎いばかりに美しい星々を引き連れて忍び寄っていた。まだ引き返すわけにはいかない。
「飲みなさい!」瑠衣子はしびれを切らして言った。