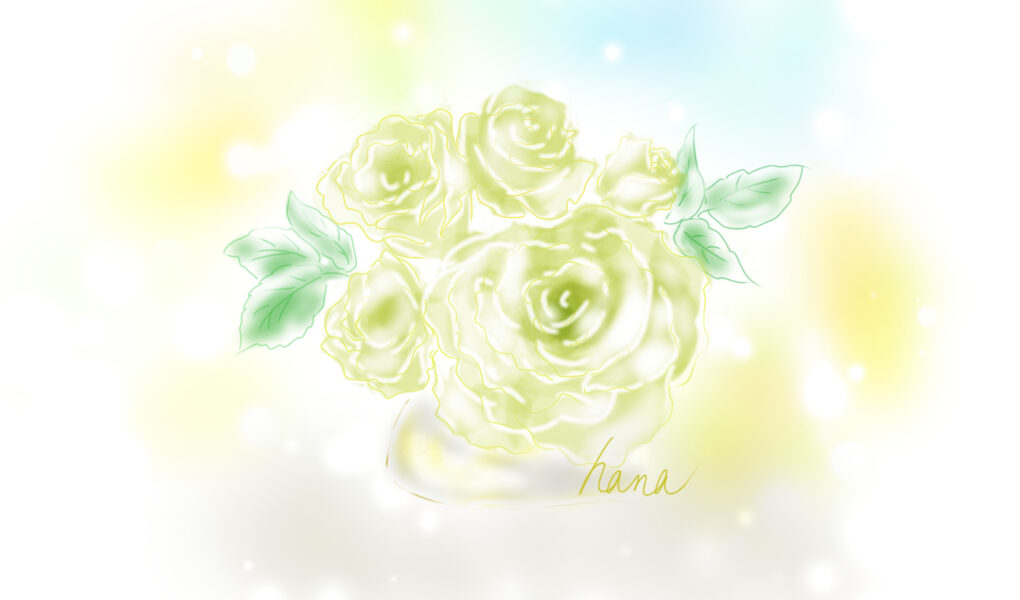3
瑠衣子はもう一度グラスをぐいっと俊一の胸元に押し出す。
飲め、と命じているのだ。駄々っ子のようなしぐさだ。
彼女がこんなに無防備なことがいままであったろうか。俊一はまた考えた。このひとときを噛みしめるように彼の思考はその場を行ったりきたりする。気だるさが誘発したただの戯れなのだ。彼女はいつだってこうなのだ。そう、そうだった、彼以外の人間には。
俊一はそれを見てきて知っていた。
例えばあのときもだ。
惰性で生きてきた瑠衣子は本人曰く――あまり勉強せず――名の知れた総合大学に入り人文学分野の学びを経て、その姿をはたから見ているぶんには、難なく卒業した。特に親しくしていたらしい男ふたり女ふたりの友達とは卒業後もしばしば会っている。仲良しグループという印象を俊一は持っているが、どこまできちんとお互いを思いやっているのかは実際のところは分からない。
気持ちのいい青空の広がる土曜日の昼下がり、久が原の家にたまたま居合わせた俊一は、初めて彼らに会った。あれからもう一年半ほどになるだろうか。
俊一はその頃理工学部の学生だった。フォルムの美しいスポーツカー二台で瑠衣子を迎えにきた彼らは、庭のヒメシャラのそばに置いた椅子に腰かけた瑠衣子に、突然のように声を張り上げた。
「ルイ、出かけようぜ」
瑠衣子は細身のジーンズとチュニックのトップスを羽織って耳にはヘッドフォンをしていた。男の声は、瑠衣子がなにかを聴きながら刺繍をしている姿に俊一が見とれていたとき彼の肩越しに放たれた。だから俊一はおどろいて、その一瞬のちには気恥ずかしさに胸が高鳴った。
俊一は彼らの車が家の塀に横づけされたことにも、彼らがその塀を伝って庭に回り込み、自分に近づいてこようとしていたことにも気づかなかった。全世界の自然音を遮断して人工的な音に没していたはずの瑠衣子が、飛び込んできた呼び声に少しのおどろきもないようすで顔を振り向けたとき、俊一と目が合った。俊一のときめきはいや増した。
瑠衣子は友達を見とめると微笑み、針を休めるために素早い動きでそれをフェルトの小さなクッションに刺した。膝から足元をおおう布を大雑把にたたみながら立ち上がり、ヘッドフォンを外して、それら一切をテーブルに放置したままこちらに歩み寄ってきた。
「電話くらいしなさいよ」
「携帯にしても出ないからさ」
「きたほうが早いと思ったのよ。ルイの刺繍する姿、相変わらず似合わなくていいね」
「きっとやっていると思って冷やかしにきたのよ」
「なに、それ」
瑠衣子も友達も軽口をたたき合って笑った。
「集中しているとさ、あたしもこう……気づかないのよね、電話とかメールとかさ。ルイと同じ」
「ね、つきあえよ。夕方には帰すからさ。こいつも時間待ちでシアターに戻るってさ」
「イベントに使うアイテムがデザイナーから搬入されるのを受け取るためだ」
「俺も新しい家のインテリアをやる人がくるから親につきあって会う予定だ。六時には帰る。リナとミユは予定がないらしい」
瑠衣子は笑った。「ふぅん。とにかく急いだほうが良さそうね」
「きみもいらっしゃいよ」
「俺のルノーに乗せてやるよ」
俊一が戸惑っていると瑠衣子が笑った。「いいのよ、俊一。おいで」瑠衣子はそう言って、「ちょっと待っていて」と庭を横切りテーブルのものをかかえて一度家屋に消えた。
「よろしくシュン。青山雄太だ」
「あたしは相川里奈」
「夏野美優」
「白野江悟だ」
それぞれは自己紹介した。瑠衣子が良い友人たちを持っている。俊一は素直にそう思った。
はにかみながら「葉山俊一です、よろしくお願いします」と声を張り上げたあと、俊一は青山雄太にしたがって彼のルノーの後部席に乗せてもらった。
ルーフはすでに収納されていて、スポーツカーに載ったことのない俊一は座り込むなり青空を見上げて、なんとも言えない解放的な気分を味わった。
瑠衣子がポシェットを斜め掛けにして出てくると、車のドアのわきで相川里奈がどうぞ、と雄太の隣に行くよう示した。
「こっちでいいわ」瑠衣子はあっさりと言って俊一の隣に滑り込んだ。
里奈は少しばかり気恥ずかしそうに笑って助手席に乗り込んだ。
「それで限られた時間でどこ行くよ?」雄太が姿勢を傾けて瑠衣子に問いかけた。
「ユータ、決めてないの。サトルは?」
「ルイが決めればついてくるってさ」
俊一が振り向くと、白野江悟が右ハンドルのポルシェの運転席に座ってこちらを見ていた。彼は手を挙げて後続する用意ができている合図をした。
瑠衣子は笑い声を立てた。「じゃぁ、久しぶりにお台場にでも行く?」
曖昧な提案だけで車は発進した。
「近場でゆっくりするのもいいね」里奈が応じた。

住宅街からたちまち混雑した大通りへ出ると、湾岸に向かった。周囲の騒音が縦横から俊一の体にぶつかってくるようだった。
「新しい家って、引っ越しするの?」瑠衣子が少し声を張り上げて質問した。
「おやじが別荘を買ったのさ、二つめを九州の由布高原に」
「ひょっとして温泉付き?」透かさず里奈が口を挟み、雄太がうなずいて笑ったのを見て「いいね!」と叫んだ。「眺望もすてきでしょうね」
「遊びにこいよ、完成したら知らせるからさ。ルイもさ」
「楽しみね」里奈がはしゃいで返した。
「そういえば俺、三ヶ月したらニューヨーク勤務だよ。と言っても半年ほどの随行だけど。新しいプロジェクトの立ち上げに駆り出されて、現地の取引先の開発をすることになってさ」
「なんだかたいへんそうだけれど楽しそうじゃない」瑠衣子が応答した。
「ユータは人当たりがいいからうまくいくわよ」里奈が激励した。
「ルイ、遊びにこいよ」
「うん、九州の別荘地なんて行ったことないし、そのうちね」
「ニューヨークだよ。マンハッタンのマンションに住むことになる。上司と同じとこだけど階がちがうからプライベートもちゃんと取れるし。たぶん俺、一週間もしたら現地での生活感が身につくはずだよ、そしたら退屈しそうだしな。きみは東京にいなくても平気だろ」
里奈が不安そうな顔になり隣の男をじっと見た。俊一はそんな里奈をそっと見守った。
瑠衣子が笑い声をたてた。「なにしに行くのよ。お金を使ってそんなところまで遊びに行きたいほど暇じゃないわ。きてほしいならみんなで一緒に行くわよ、リナもミユもサトルもね。わたしひとりで行ったらミュージカルを観て誰にも会わずに帰ってくるわ。そのほうが満喫できそうだし」
「きついなぁ、相変わらずルイは」
「みんなで行ってもせいぜい三日で帰る、そんな日程ね。わたし以外は会社員だし、そろって長期休暇が取れるとも思えないわね」
「どんなショーやっているか調べとくよ」
「いまはネットで分かるわよ」ふたりの会話に里奈が教えた。
「ユータが調べて知らせてくれなくても大丈夫ってこと」と瑠衣子が補足した。「行く日はゆっくり相談するわ。とりあえず現地勤務になったら教えてよ」
「おぅ!」
「それにしてもずいぶんな余裕ね。新規開拓に半年なんてあっという間じゃないの。遊んでいる暇ないと思うわよ」
瑠衣子の指摘に雄太は肩で笑った。「不真面目だから俺」
車はレインボーブリッジをわたった。品川駅とお台場をむすぶレインボーバスがすぐ前を走っていた。やがて彼らは大型の商業施設のひとつに立ち寄り、駐車場に車を停めた。
自由の女神像を横目にしてショッピングエリアに入り、あちらこちらのショップの品を眺めては連れの誰に似合いそうだとか、あんなのどうだ、とか勧め合って笑った。
誰も買い物をしないまま各階の通路を行き過ぎ、その後はカフェで飲料をテイクアウトして建物から出、オープンスペースに立った。
海浜公園からレインボーブリッジ、その向こうに広がる都心を眺め、時には寡黙になりながら風に吹かれた。たまにスマホを触ることはあってもおしゃべりをするときには顔をあげ、時間を共有することの意味をそれぞれに持っているような雰囲気だった。