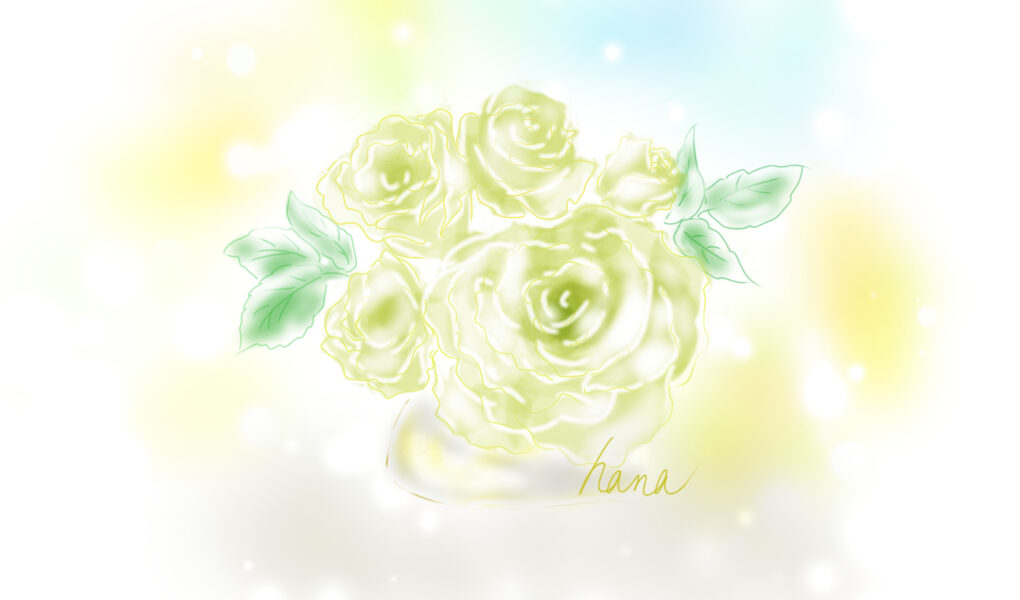2
瑠衣子は無言のまま、なにかをふりはらうように頭を揺すると、俊一の手からグラスをひったくった。「ほら、もうこれでお終いよ。新しいのを取りに戻りましょうよ」
ボトルは空になり、月明かりに浮かぶグラスの底に液体がきらめいた。彼女はかたく握り締めていたボトルを足元に転がせて、グラスをだいじそうに胸に引き寄せた。そうしながら体を横のほうにかたむけた。
「危ないですよ瑠衣子さん。そんなに覗きこんじゃ」俊一には瑠衣子が長い髪の先を湖水に浸らせたような気がしたのである。
「見えるわ、……水底に」
「えっ、なんですって」
「ふふふ」瑠衣子は気だるそうに笑い声を立てた。
彼女の話が突拍子もなく繰り出されるのはいまに始まったことではない。戸惑いを与えるほど脈絡の乏しい急展開こそ、取り巻きを翻弄し、魅了するゆえんなのだ。
俊一は思い出した。「そういえば、シャロンおばさんが書いてくれたカード、英国では親しまれている特別の鳥が描かれていましたね。幸運を呼ぶ神の鳥だって。クリスマスの時期にはサンタクロースより大忙しだってことも話してくれましたよね。瑠衣子さん、まだ持っています? 僕はだいじにしていますよ。ほら、鳥が楽しそうに雪の窓辺で歌っている……。瑠衣子さんが最後にもらっ……」
瑠衣子は素早い反応で、突き放すように言った。「ママは素敵なカードを置いてわたしから去ったわ」少し間を置いて彼女はつづけた。「慈愛の心を教えようとした立派な母親だったとパパは言った。いまは計り知れない世界にいるのね」
吸い込まれそうな揺らめきを覗いたまま、瑠衣子は黙した。彼女には昔から妙に取りつきにくい大人らしい顔と、こちらが思わず気高さを覚まされるような純真な一面があった。俊一は高まりつつある官能の夢を冷まされるような会話を避けたかった。ほんの小さな葉音が耳元を掠めたとき、俊一は辺りをそっと伺った。いわれない不安が彼を去来していた。
「キスしたいわ。でも届かない、もう少しなのに」彼女はグラスを水上にかたむけた。
わずかな液体が湖面に散ったのかどうか、俊一には目視できなかった。薄闇をたわませる怪しいさざ波に溶融して、クラレットの赤いしずくがまだらの一部になったように思えたのは、グラスの柄をにぎったまま肘を大きく開いた瑠衣子のしぐさに、彼の想像力が反応したせいでもあった。
「俊一! 月がほら、ごらんなさいな」
彼女がなにに心打たれたのか……。雲はゆるやかに流れ、月は皓々と照り、星はきらめいていた。分かりきったことだったが、瑠衣子は空を見上げてはいなかった。それで俊一はすぐにまた湖面を見下ろした。彼の傍らにも月らしきものはあって、頭上の光景をあやなす水面の浮遊物としてひらひらと舞っていた。
俊一は水鏡に照り映えて柔らかく明滅する瑠衣子の面差しをたどった。非のうちどころのない、紛うことなき横顔がそこにあった。だがそれは凍りついたようにじっと動かず、しかるに俊一には、瑠衣子がただ水底深い闇を見つめているとしか思われなかった。