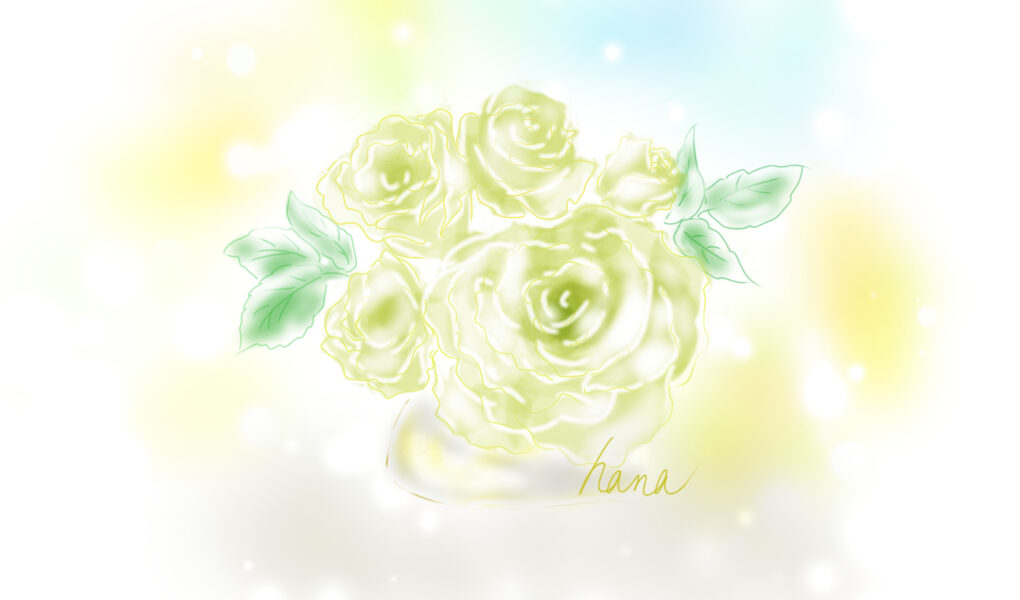1
ボートに誘う俊一の申し出に応じたのも定まらない気分のせいだったかもしれない。
瑠衣子が外気に当たろうとして建物を出たとき全員で同行したが、もう日も暮れており、迫りくる連山がうっすらと星空のしたに稜線を浮かびあがらせていた。こぼれそうな星々をあおいで心打たれた雄太と里奈はその場にたたずみ、そのようすを横目に瑠衣子は林のほうに足を延ばした。
俊一は瑠衣子を追った。
やがてボート乗り場に出た瑠衣子は、湖面に足を投げ出すようにして桟橋に座った。ワインボトルとグラスを彼女は胸に抱いていた。俊一は冗談のように見せかけて瑠衣子を船遊びに誘った。それが成功して瑠衣子は自らボートに乗ったのだ。
「瑠衣子さん、青山さんと相川さんは僕らを探しているかもしれませんね」
「そうね」瑠衣子はどうでもいいことのように応じた。
「別荘に戻って東京へ帰るって言ったら青山さんが明日送るって申し出るかもしれませんね。そしたら僕も同行していいですか」
「あの人たち、今回は車じゃないわよ」
「そうですけど、瑠衣子さんが高野さんの運転で帰るって言ったら、一緒にきそうじゃないですか」運転手の高野はまだ三十代だが、わきまえのあるきちんとした性分で俊一も気に入っていた。
「送ってくれるのとはちょっとちがうけれど」瑠衣子は戯れの考察を楽しむように高笑いした。「いずれにしてもそうね、だから戻りましょう」
「ただね、僕は賛成できません」俊一は瑠衣子に説明調になった。「やっとマスコミの目を逃れてきたのに――。半年前の事件でも世間に出たのは二週間前です。瑠衣子さんのあの写真のせいか、なんとなく妙な方向にエスカレートしていませんか。あの写真については青山さんたちと話したことに僕も異論がありません。少しアングル的に不自然なのは撮っているとき、たまたま見ていた第三者が携帯で撮影して、それを削除せずにずっと端末に入れたままにして、今回の騒ぎに乗じてマスコミに売ったかSNSにあげたというしろものだからでしょ。その不埒な人間はあのパーティーの場に居合わせた者だが特定ができない。まったくどんな得があったんでしょうね」
俊一の愚痴めいた言いぐさに瑠衣子はまたクスクスと笑った。
瑠衣子はきょう、刺繍もやらずに来客の相手をした。幼少期から母の手製の洋服やインテリアに囲まれて育った瑠衣子は、かすかに記憶に残る母のまねをして、そうすることで母と時間をともにするために針と糸を持って淡色の布に想いを描いている。そう大人たちが解釈していて、俊一にもそのように聴かせていたから、彼もずっとそれを信じている。それはいまや瑠衣子の心を強化しリフレッシュする行為でもあるのだと理解する。きょうだって静かにそれをすることもできたのに、楽な道を取らず、ふいの訪問客の相手をした。
「そういえば、寺脇麻里さんはお元気ですか。あ……、公演は確か明日からでしたよね」
「思い出したのね」
瑠衣子は肩書きを好まないようだが、刺繍作家と言ってもいいと俊一は思っていた。
母のシャロンを知っている手芸店に瑠衣子も幼少期から出入りしていた。母の影響で瑠衣子が刺繡をしていることはその店の主である女も知っていた。二年ほど前のある日、瑠衣子は材料の買い足しに行き、どんなものをいまは作っているのかと質問された。そのとき薄い素材の生地で作った肩掛けや小物入れなどの写真を瑠衣子は見せた。店主はたいそう気に入り、店に置かせてくれないかと申し出た。そんな縁で瑠衣子はたまにお手製の品を卸すようになっていた。派手やかに遊びまわる外でのようすとはあまりにもちがう、そんな創作家としての瑠衣子の姿に触れると、俊一はいつも切なさと幸せで胸がいっぱいになっていた。
寺脇麻里は十歳のバレリーナだ。バレエでロンドンに留学する前、母親と立ち寄った手芸店で瑠衣子の作ったフリルのついたエプロンに出合った。刺繡のきれいなそれを母子ともに気に入り、子ども用のサイズで作ってほしいと店主経由で求めてきた。以来、縁ができて瑠衣子は麻里のために巾着袋やハンカチなどに刺繍をしてはその母が立ち寄ったときにわたしてくれるよう店の主経由でプレゼントしていた。
直接の交流を避けているのは、人間関係が深まることを瑠衣子が好まないからだと俊一は思っている。寺脇麻里は、子どもが主役のバレエ作品の主要な役を踊るために一時帰国することを、その店経由で知らせてきていた。店の主は店内にも置いた公演のフライヤーと、寺脇真理が託した瑠衣子への招待券を送ってきていた。